ここでは相続税の申告で活用されることのある書面添付制度や、その書面添付制度のメリットとデメリットについて解説します。
そもそも相続人側は相続税の税務調査はできるだけ避けたいと考えるもの。
税務調査を受けることになると、そのための時間や準備が必要になって不必要なコストが発生してしまいますし、税務調査に馴れていなければ緊張やストレスも伴います。
ですが、やむを得ずに税務調査の対象になってしまうことがありますし、例えば税理士に依頼せずに自分自身で申告し、その申告に誤りがあれば調査の対象になってしまうこともあります。
資産の評価や、例えば小規模宅地等の特例を活用できるかどうかは専門的な判断が必要ですので、馴れていない方が判断するとミスが生じやすいのではないかと感じます。
ここからは相続税に関する税務調査に関連して、書面添付制度について説明します。
目次
相続税申告における書面添付制度とは
まずは簡単に書面添付制度について説明します。
書面添付制度とは、税理士自身が関与した相続税の申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を書面として申告書に添付すれば、税務調査の通知前に、税理士に意見を述べる機会が与えられる制度のことです。
もう少し噛み砕いて説明すると、相続税の申告にあたって実施した税理士側の作業の内容や判断の根拠などを書面に記載し申告書に添付して提出すれば、税務調査の前に税理士に意見を述べる機会が与えられ、その意見によって税務署側の疑問や不審点などが解消されれば、税務調査が省略されることにも繋がる制度のことです。

この書面添付制度があることで、税務署側にとっても業務が効率化され、疑問の多い相続案件に対して税務署側の限られたリソースを集中的に投入できることにもなります。
相続税申告における書面添付制度のメリット
相続人側にとって、この書面添付制度を利用すれば、一般的に次のようなメリットがあると言われています。
税務調査の可能性が低くなる
書面添付制度を活用すると、実際に税務調査の確率は低くなるというデータがあります。
税務調査の前に税理士に意見聴取がある
税理士に依頼しなかったり、税理士に依頼しても書面添付制度を活用しないときには、税務調査になってしまう可能性はあるのですが、書面添付制度を活用すれば、まずは税理士に対して意見聴取が行われ、その結果、税務署側の疑問や不審が解消したときには税務調査は省略されることになります(税務調査が省略される可能性が高まる)。
過少加算税は免除される
税理士に対する意見聴取のときに誤りが発見され修正申告をしても本税(相続税)は納付する必要がありますが、過少申告加算税は免除されます。
この点も不要な支出は回避できるというメリットがあります。
相続税申告における書面添付制度のデメリット
これに対して、書面添付制度を活用するデメリットは次のような点にあります。
添付書面の作成にコストが発生する
まず1つ目のデメリットについて言うと、税理士側にとっては添付書面作成という手間が発生しますし、依頼者側(税理士に申告を依頼する相続人)にとっても書面の作成のための金銭的コスト・費用が発生してしまいます。
税理士側に添付書面の作成という作業が発生してしまいますし、相続人は上で説明した書面添付制度のメリットを受けることになりますので、その対価が発生してしまうのはやむを得ないでしょう。
添付する書面に虚偽の記載をすれば税理士が処分される
2つ目のデメリットは相続人にとってのデメリットではなく、税理士にとってのデメリットと言えます。
基本的に税理士は書面に虚偽の記載をすることはありませんが、虚偽は記載できないというプレッシャーはかかることになります。
税理士が処分される可能性があるので、書面添付制度を活用したがらない税理士もいるのが現状です。

相続税以外の税金
最後に補足として、相続税の申告でミス等があった場合の税金について簡単に説明します。
相続税の申告でミスがあった場合には、次のような税金が発生することになります。
- 延滞税
申告が遅れたことに対して課される税金 - 無申告加算税
正当な理由なく期限内に申告しなかったために課される税金 - 重加算税
申告に仮装や隠ぺいがあった場合に課される税金 - 過少申告加算税
期限内に提出された申告書に記載された相続税が過少であった場合に課される税金
相続税の申告でミスがあると、このような不必要な税金が発生してしまいますので、できれば申告ミスは避けたいところです。
因みに、相続税の税務調査の状況については、リンク先で国税庁が公表しているレポートを基に解説しています。ご興味のある方はご覧ください。
書面添付制度のまとめ
ここまで説明したように、書面添付制度は税理士側の作業によるものです。
ただ書面添付制度を活用したからといって、絶対に税務調査が回避されるわけではありません。
この点は、誤解ないようお願いします。

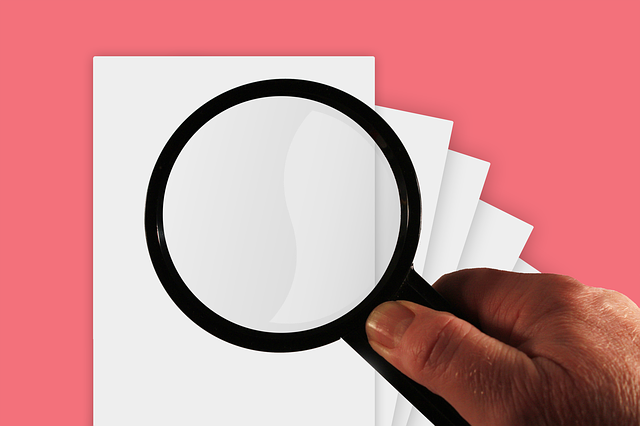

 お気軽にお問合せください
お気軽にお問合せください
