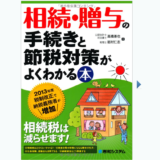相続が発生したときには、必ずしも相続税を申告する必要はありません。ただ課税価格の合計額が基礎控除額よりも大きい場合には相続税を申告することになります。
ですので、富裕層以外の方は必ずしも相続税の申告をするとは限らないことになりますし、課税価格の合計が基礎控除額よりも少しでも大きければ相続税の申告をする必要があります。
今回は相続税申告の要否が3つのステップで簡単にわかる簡易判定の仕方について解説します。
まずはこの方法で相続税の申告が必要か否かを(簡単に)把握しておきましょう。
目次
3つのステップで相続税申告の要否を簡易判定
まずは3つのステップで相続税申告の要否を判断するための流れについて確認します。
このような3つのステップで相続税の申告の要否を判断します。
ステップ1.基礎控除額の算定
まずは相続人の数を確定して基礎控除額を求めます。
基礎控除額の算定は次の通りです。
次の表は基礎控除額の速算表です。この速算表を使えば、簡単に基礎控除額を求めることができます。
計算例
相続人3人は4,800万円(=3,000万円+600万円×3名)
| 相続人の人数 | 基礎控除額 |
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
| 6人 | 6,600万円 |
| 7人 | 7,200万円 |
| 8人 | 7,800万円 |
相続人は次のような順番で、相続人が決まります。配偶者は(生きていれば)必ず相続人になります。
| 相続人の順位 | |
| 第1順位 | 子(代襲相続あり) |
| 第2順位 | 直系尊属 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(代襲相続あり。再代襲はなし。) |
子がいれば、配偶者とともに子が相続人になります(第1順位)。子がいなければ、父母などの直系尊属が相続人に(第2順位)、直系尊属がいなければ被相続人の兄弟姉妹が相続人になります(第3順位)。
誰が相続人になるかについての詳細は、リンク先の記事で確認できます。
ステップ2.相続財産と債務等を集計
基礎控除額を算定した次に、相続財産と債務等を集計します。まずはどのような相続財産(借金などの債務を含む)があるかをリストアップしましょう。もちろん相続財産をリストアップするだけでなく、その財産の「金額」も確認する必要があります。
| 相続財産又は債務 | 金額 |
| 不動産 | 円 |
| 有価証券 | 円 |
| 貯預金 | 円 |
| 保険金 | 円 |
| 被相続人から生前贈与等 ※ | 円 |
| 借入金等の債務 | ▲ 円 |
| 葬式費用 | ▲ 円 |
| ② 課税価格の合計 | 円 |
※ 相続開始前3年内の贈与や相続時精算課税適用財産など
ステップ3.相続税申告の要否を判定
最後に相続税申告の要否を判定します。
ステップ1で計算した基礎控除額からステップ2で集計した課税価格の合計を控除します。
課税価格の合計額が基礎控除額よりも小さいならば、相続税の申告は不要です。

また不動産や株式等の相続財産の評価については、誰が評価するかで評価額が異なることがあります。相続財産の評価を巡って国税局の税務調査が入り、億単位の追徴課税をされることもありますので注意が必要です。
相続税の納付額の具体的な計算の仕方についてはリンク先の記事で確認できます。

ここでご紹介した相続税申告の簡易判定は、国税庁で公表している相続税の簡易判定の仕方と同様の方法です。相続税申告の要否についてご心配な方は、是非、一度お試しください。また明らかに相続税の申告が不要な方以外の方は、税理士に相談することをお勧めします。
不動産や有価証券など相続財産の評価には、専門的な判断が必要だからです。



 お気軽にお問合せください
お気軽にお問合せください